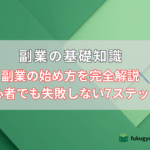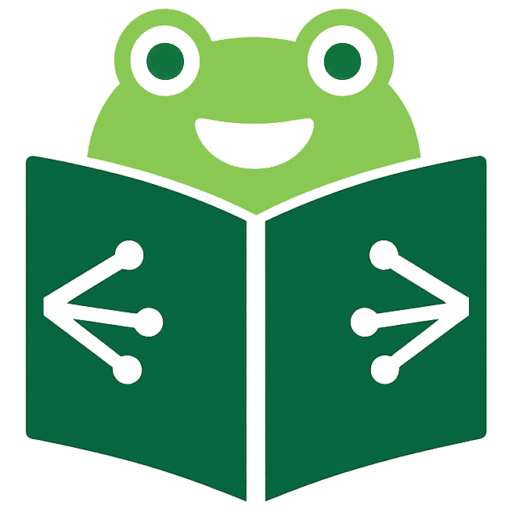はじめに:副業の“会社バレ”は、住民税の扱いが9割
会社員の副業が発覚する最大の原因は住民税の特別徴収(給与天引き)です。
副業分まで合算された住民税額が会社に通知され、前年との差から気づかれる──この流れが王道パターン。
対策の本丸は、副業分の住民税を「普通徴収(自分で納付)」に切り替えることです。
本記事では、
- 「そもそも住民税とは何か」
- 「20万円ルールと住民税の関係」
- 「普通徴収に切り替える具体手順(確定申告あり/なしの2通り)」
- 「自治体ごとの申請欄の違い」
を、書き方見本・文面例つきで徹底解説します。
目次
- 会社員の住民税はなぜ“会社経由”になるのか(特別徴収)
- 20万円以下でも必要?──所得税ルールと住民税ルールの違い
- 副業バレを防ぐ鍵:「普通徴収」とは何か
- 普通徴収への切替手順(A:確定申告する/B:確定申告しない)
- 自治体ごとの書式・チェック欄の違いと対処法
- よくある失敗(会社に通知される設定)と回避策
- ケース別Q&A(Wワーク・給与副業/業務委託/物販/少額収入)
- 記入例サンプル(文面そのまま使えるテンプレ)
- 申告後にやることチェックリスト(納付書・納付期日・保管)
- まとめ:合法かつ正確に“自分で納付”へ
1. 会社員の住民税はなぜ“会社経由”になるのか(特別徴収)
住民税(市県民税)は前年の所得に対して、翌年6月〜翌々年5月の1年分を納付します。
会社員の場合、原則として会社が特別徴収(給与天引き)でまとめて納めます。
- 特別徴収:会社が毎月の給与から天引き→市区町村へ納付
- 普通徴収:本人に納付書が届き、コンビニや口座振替で自分で納付
副業の所得があると、市区町村側で本業給与+副業所得を合算して住民税を計算。
特別徴収のままだと、その合算結果が会社へ通知され、結果として「額が増えた理由」を疑われやすくなります。
2. 20万円以下でも必要?──所得税ルールと住民税ルールの違い
ここで重要なのが、所得税の「20万円ルール」と住民税は別物という点。
- 所得税:給与以外の所得が年間20万円以下なら、確定申告不要(会社員の特例)
- 住民税:金額に関わらず、基本的に申告が必要(自治体への報告義務)
つまり「20万円以下だから何もしない」はNG。
住民税の申告を行い、普通徴収(自分で納付)にする意思表示が大切です。
3. 副業バレを防ぐ鍵:「普通徴収」とは何か
普通徴収にすると、副業分の住民税はあなた宛てに納付書が来るため、会社に通知されません。
一方、本業分の住民税はこれまで通り会社の特別徴収で天引きされます。
この“分割”がミソです。
ポイント
- 本業の住民税=特別徴収(会社)
- 副業の住民税=普通徴収(自分で納付)
という“併用”が可能
4. 普通徴収への切替手順(A:確定申告する/B:確定申告しない)
A. 確定申告をする(副業所得が20万円超 等)
- 申告方式で「住民税に関する事項」を開く
- 「自分で納付(=普通徴収)」にチェック
- 給与以外の所得(雑/事業)を正確に入力
- 送信(e-Tax)または書面提出
- 春〜初夏:自治体から副業分の納付書があなたの住所へ届く
- 期日までに納付(年4回 or 一括)
備考欄に一言
「給与所得以外の住民税は普通徴収を希望します。」
と明記しておくと確実性が上がります。
B. 確定申告をしない(20万円以下の会社員特例を使う場合)
- 自治体の住民税申告書を取り寄せ(サイトDL or 郵送請求)
- 副業分の収入・必要経費・所得を記載
- 「普通徴収」欄に✓(見当たらなければ備考に明記)
- 身分証・控除証明(生命保険・地震保険等)を添付
- 期日までに提出(窓口/郵送)
- 後日、あなた宛てに納付書が届く→納付
住民税申告書に“普通徴収”チェックが無い自治体もあります。
その場合は備考欄に明記し、封筒の余白にも赤字で
「給与等以外の所得は普通徴収希望」
と書いておくと事務的に通りやすいです。
5. 自治体ごとの書式・チェック欄の違いと対処法
自治体によって、
- 「給与分は特別徴収、その他は普通徴収」と選択肢が分かれている
- 「特別/普通」の切替チェック欄が無い
など様々です。
対処の型(テンプレ)
- チェック欄がある → その他所得=普通徴収にチェック
- チェック欄がない → 備考欄へ明記(文例は後述)
- オンライン申告フォーム → 自由記述に普通徴収希望を記載
窓口・電話相談でも、
「会社に副業分がいかないよう、給与以外の所得は普通徴収にしたい」
と伝えると、担当課が案内してくれます。
6. よくある失敗(会社に通知される設定)と回避策
| 失敗例 | 何が起きるか | 回避策 |
|---|---|---|
| 「特別徴収」に✓して提出 | 副業分も会社へ通知される | 必ず「普通徴収」へ✓ |
| 住民税申告を出さない | 自治体側が推計課税→特別徴収へ乗る可能性 | 20万円以下でも必ず申告 |
| 給与副業(Wワーク)を申告 | 2社給与は特別徴収が原則→本業へ合算されやすい | 給与型副業は業務委託化をご検討 |
| 住所変更漏れ | 納付書が届かず滞納→会社関与の是正も | 住民票・マイナンバーカードの住所更新を即時 |
7. ケース別Q&A(Wワーク・業務委託・物販・少額)
Q1:週末アルバイト(給与)で月3万円。普通徴収にできますか?
→ 給与は原則、特別徴収。2カ所給与は合算され本業の特別徴収へ反映されやすく、会社に伝わる可能性が高いです。
バレ回避を重視するなら、**給与型ではなく業務委託(報酬)**へ切替交渉、または給与副業を避けましょう。
Q2:クラウドソーシング(報酬)で年間15万円。確定申告なしでOK?
→ 所得税は特例で申告不要でも、住民税の申告は必要。
住民税申告書で**普通徴収へ✓**してください。
Q3:物販(せどり)で赤字。申告は?
→ 住民税は所得(収入−経費)ベース。赤字なら税額は出ませんが、申告して事実を伝えるのが安全。
来年以降の課税誤りも防げます。
Q4:本業の年末調整だけで終えたい。副業はどう扱えば?
→ 住民税は別申告。普通徴収にして会社ルートに乗せないこと。
8. 記入例サンプル(そのまま使えるテンプレ)
8-1. 住民税申告書(確定申告なしのケース)
- 所得区分:雑所得/事業所得 に該当金額を記入
- 控除:基礎控除・社会保険料控除など該当分を記入
- 徴収方法:その他所得=「普通徴収」に✓
- 備考欄: 「給与所得以外の住民税は普通徴収(自分で納付)を希望します。
会社(特別徴収)へ合算されないよう取扱い願います。」
8-2. 確定申告書(確定申告ありのケース)
- 「住民税・事業税に関する事項」欄
→ 「自分で納付(普通徴収)」に✓ - 備考欄: 「給与以外の所得分の住民税は普通徴収を希望します。」
8-3. 申請書がオンラインの自治体(自由記述)
「副業(雑所得/事業所得)分の住民税は、普通徴収(本人納付)でお願いします。給与分は従前どおり特別徴収で問題ありません。」
9. 申告後にやることチェックリスト
- 自治体からの納付書が届くか確認(届かない時は税務課へ連絡)
- 納付期日をカレンダー登録(年4期 or 一括)
- 口座振替 or 地方税統一QR支払い登録(コンビニ可)
- 翌年6月の会社の住民税通知に副業分が混ざっていないかチェック
- 仕訳・帳簿・領収書は7年保管(電子保存も可)
10. まとめ:合法・正確に“自分で納付”へ
- 20万円以下でも住民税は原則申告が必要
- 普通徴収(自分で納付)に切替えると、会社通知を回避できる
- 給与型副業は注意:合算・特別徴収に乗りやすい
- 申告書に明確な意思表示(普通徴収希望)を残す
- 申告後の納付書・期日管理までやり切る
“隠す”のではなく“正しく分けて支払う”。
これが合法的に会社バレを避ける最短ルートです。副業の継続性と安心のために、今期から住民税の扱いを整えておきましょう。