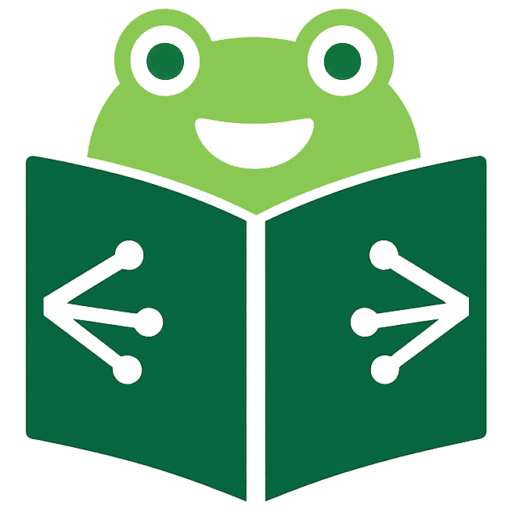はじめに:副業を始めたら「扶養の壁」に注意!
「副業をしたら扶養から外れるって本当?」
「103万円・130万円・150万円の壁って何が違うの?」
これは副業やパートを始めた人の最初の大きな悩みです。
実は「扶養から外れる」という言葉には、
・税金上の扶養(配偶者控除)
・社会保険上の扶養(健康保険・年金)
という2つのまったく別の意味があります。
この2つを混同すると、思わぬ税金や保険料の負担が発生することも。
この記事では、「税金の扶養」と「社会保険の扶養」の両方を整理しながら、
103万・106万・130万・150万ラインの違いを正確に理解できるように丁寧に解説します。
目次
- 「扶養」には2種類ある:税金と社会保険
- 【税金上の扶養】配偶者控除・配偶者特別控除の仕組み
- 【社会保険上の扶養】健康保険・年金の扶養条件
- 103万円・106万円・130万円・150万円の壁とは
- 税金と保険、それぞれの影響を表で整理
- 副業やパートで扶養を外れるケースとその影響
- 収入を抑える?それとも外れる?判断基準とシミュレーション
- 会社員・主婦・学生など立場別の注意点
- 扶養から外れたときの手続きと戻る条件
- まとめ:扶養ラインを理解して損しない副業を
1. 「扶養」には2種類ある:税金と社会保険
まず最初に押さえておきたいのが、扶養には2種類あるということです。
| 区分 | 管轄 | 対象 | 影響するもの |
|---|---|---|---|
| 税金上の扶養 | 税務署 | 配偶者控除・扶養控除 | 所得税・住民税 |
| 社会保険上の扶養 | 健康保険組合・年金機構 | 被扶養者認定 | 保険料負担の有無 |
つまり、
- 税金上の扶養を外れる → 控除が減って家族の税金が増える
- 社会保険の扶養を外れる → 自分で保険料を払う必要がある
という、全く別の影響が出ます。
2. 【税金上の扶養】配偶者控除・配偶者特別控除の仕組み
● 配偶者控除
配偶者の年間所得が48万円以下(給与収入103万円以下)の場合、
主たる納税者(夫など)は最大38万円の所得控除を受けられます。
● 配偶者特別控除
所得が48万円超~133万円以下(給与収入103万~201万円以下)なら、
段階的に控除が減額されます(最大38万円 → 最小1万円)。
| 配偶者の年収 | 控除の種類 | 控除額 |
|---|---|---|
| 103万円以下 | 配偶者控除 | 38万円 |
| 103万~150万円未満 | 配偶者特別控除 | 38万円 |
| 150万~201万円未満 | 配偶者特別控除 | 減額あり |
| 201万円以上 | 控除なし | 0円 |
つまり「103万円を超えてもすぐに損ではない」ですが、
150万円を超えると控除が大きく減るため注意が必要です。
3. 【社会保険上の扶養】健康保険・年金の扶養条件
社会保険の扶養は、収入が一定以下であることが条件です。
このラインを超えると、自分で健康保険料と年金保険料を負担しなければなりません。
● 一般的な目安(協会けんぽ等)
- 年収130万円未満
- 月収108,333円未満(交通費込み)
- 被扶養者として認定される
● 一部大企業・パート先による例外(106万円の壁)
次の条件すべてに当てはまる場合、年収106万円でも社会保険加入が義務になります。
- 従業員数101人以上の会社
- 勤務時間が週20時間以上
- 月収8.8万円以上(年収106万円)
- 勤続1年以上見込み
- 学生でない
4. 103万円・106万円・130万円・150万円の壁とは
これらの「壁」は、税金・社会保険それぞれの制度上のボーダーラインを示しています。
| 壁 | 種類 | 内容 | 影響 |
|---|---|---|---|
| 103万円の壁 | 税金 | 配偶者控除の対象 | 扶養控除が消える(所得税・住民税UP) |
| 106万円の壁 | 社会保険 | 一部大企業勤務者のパート対象 | 社保に自分で加入(保険料負担増) |
| 130万円の壁 | 社会保険 | 一般的な扶養判定基準 | 保険料を自分で負担する必要が出る |
| 150万円の壁 | 税金 | 配偶者特別控除の満額終了 | 控除が減り、税負担が増える |
簡単に言うと:
- 103万円=税金の第一関門
- 130万円=社会保険の第一関門
- 150万円=税金上の最終関門
5. 税金と保険、それぞれの影響を表で整理
| 項目 | 税金上の扶養 | 社会保険上の扶養 |
|---|---|---|
| 管轄 | 税務署 | 健康保険組合・年金機構 |
| 影響範囲 | 所得税・住民税 | 保険料・年金 |
| 判定基準 | 年収103万/150万ライン | 年収106万/130万ライン |
| 外れた場合 | 控除が減り家族の税金増 | 自分で保険料支払い |
| 復帰条件 | 翌年に所得を下げる | 一定期間後、再申請可能 |
6. 副業やパートで扶養を外れるケースとその影響
ケース①:年収105万円の副業(ライター+パート)
→ 税金上は配偶者特別控除対象(扶養OK)
→ 勤務先が大企業で週20時間以上なら社会保険加入(106万円の壁)
ケース②:年収130万円を超えるネット物販副業
→ 税金上は控除一部あり(150万まで)
→ 社会保険の扶養から外れるため、健康保険・年金を自分で負担(年間20~25万円増)
ケース③:年収160万円の動画編集副業
→ 税金上も社会保険上も扶養から外れる
→ 税金UP+保険料負担で実質手取り減
7. 収入を抑える?それとも外れる?判断基準とシミュレーション
【A】扶養内で働くパターン
- 年収:103万円以下(税・社保どちらも扶養)
- 手取り:約103万円(税・保険ほぼゼロ)
【B】130万円で止めるパターン
- 社会保険は扶養、税は配偶者特別控除
- 家族の控除を維持しつつ収入UP
【C】150万円以上稼ぐパターン
- 税・社保とも扶養外
- 自分で国保・国民年金を支払い
- 経費・青色申告で節税すれば手取りアップも可能
シミュレーション(概算)
| 年収 | 税金・保険 | 手取り | 備考 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | ほぼゼロ | 約100万円 | 扶養内維持 |
| 130万円 | 税・社保扶養 | 約125万円 | 限界ライン |
| 160万円 | 社保加入・税発生 | 約130万円 | 自立開始ライン |
| 200万円 | 青色申告活用 | 約155万円 | 節税効果あり |
8. 会社員・主婦・学生など立場別の注意点
| 立場 | 注意点 |
|---|---|
| 主婦(夫の扶養) | 年収130万円未満を意識。パート勤務先が大企業なら106万ラインも注意。 |
| 学生 | 親の扶養は「年収130万円未満」。アルバイト+副業の合計で判定される。 |
| 会社員 | 自分の副業で扶養家族が外れるケースも。配偶者控除・子ども手当への影響あり。 |
| フリーランス夫婦 | それぞれが個人事業主として登録し、扶養制度を使わないほうが有利なことも。 |
9. 扶養から外れたときの手続きと戻る条件
● 扶養から外れたとき
- 健康保険組合・勤務先に報告
- 被扶養者削除の手続き
- 自分で国民健康保険・国民年金へ加入(市区町村)
- 翌年の確定申告で配偶者特別控除の適用可否を確認
● 扶養に戻る条件
- 年収が再び130万円未満になった場合
- 一定期間安定して収入減が確認できれば再申請可
10. まとめ:扶養の「税」と「社保」は別物。正しく理解して損を防ぐ
- 扶養には「税金」と「社会保険」の2種類がある
- 103万円/150万円=税金の壁
- 106万円/130万円=社会保険の壁
- 税金上の扶養を外れると家族の控除が減る
- 社会保険の扶養を外れると自分で保険料を払う
- 節税・青色申告で“扶養外でも得をする”働き方が可能
収入を「抑える」よりも、「外れても損しない準備」をすることが現代的な選択肢です。
freeeやマネーフォワードなどの会計アプリで収入を管理し、翌年の所得予測をしておくのがおすすめです。
よくある質問(FAQ)
Q1. 103万円を1円でも超えたら控除なし?
→ 配偶者特別控除で150万円までは段階的に控除あり。
Q2. 社会保険の扶養を外れたらいつから保険料発生?
→ 外れた月の翌月分から国民健康保険・国民年金の負担が始まります。
Q3. 扶養を外れても戻れる?
→ 年収が安定して130万円未満になれば再認定可能。
Q4. 副業の種類(物販・ライターなど)で判定に違いは?
→ 違いなし。すべて「年間の所得額(収入−経費)」で判定されます。